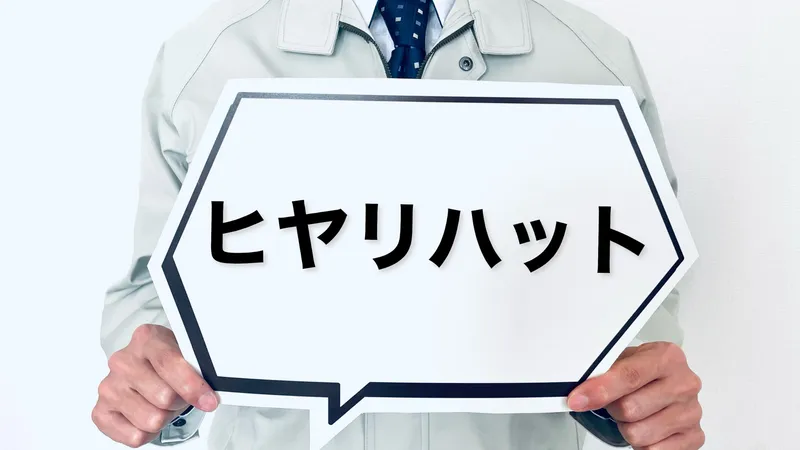
重大な事故につながる一歩手前を意味する「ヒヤリハット」。感電事故や転落事故のリスクが常に付きまとう電気工事においては、ヒヤリハット事例を分析し、それらが重大な事故につながらないように再発防止対策を講じることが非常に重要となります。
そこで今回は、電気工事を行う際に起こりがちな5つのヒヤリハット事例をご紹介します。実際にどのようなシーンでヒヤリハットが発生したのかを知識として知っておくだけでも安全対策になりますので、ぜひ最後までご覧ください。
ヒヤリハットとは?
「ヒヤリハット」とは、業務や日常の中で一歩間違えば事故や災害につながっていたかもしれない、「ヒヤリ」としたり「ハッ」としたりするような危険な出来事を指します。
ヒヤリハットは意味だけを捉えれば、「結果的に何も起きなかった」という状況であること、また、日常のちょっとした出来事であることも多いため、軽く考えてしまうことも少なくありません。しかし、これは幸いにも重大な事故につながらなかったというだけで、事故や災害に直結する一歩手前の状況であることを理解しておくことが大切です。
特に、電気を取り扱う工事においては、ちょっとした油断が事故につながります。そのため、ヒヤリハット事例を分析して要因を特定しておくことが、電気工事における安全対策の一つとなるのです。
次から電気工事におけるヒヤリハット事例について、どのようなシーンで発生したのか、またその原因と対策をご紹介していきますので、安全計画の参考にご覧ください。
電気工事のヒヤリハット事例1:はしごの転倒

ヒヤリハットの発生状況
屋外でアンテナ工事を行う際に、屋根に上るためのはしごを立てかけていた。その日は少し風の強い日だったが、車に工事道具を取りに行っている間に風が強く吹き、はしごが倒れてしまった。
住人や通行人などには当たらなかったため、怪我人が出なかったのは幸いだが、お客様の車に当たってしまい、物損事故となってしまった。
対策
風が強い日にもかかわらず、はしごが倒れることはないだろうと思い込み、その場を離れてしまったのが原因。今後の対策としては、「はしごはちょっとした油断で倒れるもの」だとして、立てかけた後にずれたりぐらついたりしないか、入念に安全管理を行うようにする。
電気工事のヒヤリハット事例2:ブレーカーがオンのまま配線作業
ヒヤリハットの発生状況
配線接続作業において、分電盤内のスイッチに配線を接続しようとした際、そちらの配線が接続されていないにもかかわらず、既にブレーカーがオンになっていた。もし、それに気付かずに分電盤のスイッチにケーブルを接続していれば、感電する危険があった。
対策
作業前に、検電ドライバーで活線でないかどうか、またブレーカーはオフになっているかどうかなどを確認していなかったのが原因。現場の確認不足がヒヤリハットを招いた。今後の対策としては、作業前に活線状態やブレーカーの状態を十分に確認するほか、万が一に備えて、絶縁保護具の着用や接触防止カバーの設置などを行うようにする。
出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト 労働災害事例」
電気工事のヒヤリハット事例3:電源の切り忘れ
ヒヤリハットの発生状況
金属の溶接で使用する機械の点検作業中に、電源のメインスイッチを切り忘れたまま作業を行おうとした。端子部をパンチで取り外す際に気付いたため感電事故は防げたが、そのまま電気の通っている端子部に触れていたら感電事故につながっていた可能性がある。
対策
あらかじめ、作業前に電源が切れているかどうかを確認しなかったことが原因。今後の対策としては、電気機器の点検を行う際には、必ず元電源を切ることを周知。作業前から作業後の処理まで、作業員には作業工程をしっかりと教育し、理解してもらうようにする。
出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト 労働災害事例」
電気工事のヒヤリハット事例4:撮影に気を取られてあわや感電
ヒヤリハットの発生状況
受電設備の月次点検で、電灯変圧器の銘板を記録しようと、撮影に気を取られていた。そのため、うっかり充電部にある変圧器用の高圧交流負荷開閉器(LBS)に接触し、感電してしまうところだった。
対策
他のことに気を取られて、不用意に受電設備内をのぞき込んでしまった“うっかり”が原因。そのため、作業時には細心の注意を払うように安全教育を行うほか、作業前に通電状態を確認してから点検を実施する、また、電気が止められないときは、感電対策を行うなどで対応する。
出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト 労働災害事例」
電気工事のヒヤリハット事例5:工具の落下
ヒヤリハットの発生状況
新たな回線を設ける際、受電設備に新規の電線を接続するために、絶縁用のゴム板を設置しようとしていた。その際に、充電部に工具を落としてしまった。
対策
電気工事用の工具を持ち込む際、落としてしまわないように落下防止対策を怠っていたのが原因。工具の落下によって感電事故を招いてしまったり、下に人がいた場合には怪我を負わせてしまう可能性があるため、工具類が落ちないように滑り止めを使用して落下防止対策を行うほか、工具の落下を見越して、周辺を立ち入り禁止にするなどで対応する。
出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト 労働災害事例」
電気工事のヒヤリハットを防ぐには?

感電や転落などの重大な事故を防ぐためには、これらのヒヤリハット事例の原因を分析し、しっかりとした再発防止対策を行うことが大切です。
今回、電気工事におけるヒヤリハットとしてご紹介してきた事例では、ちょっとした油断が招いた事例も少なくありません。「作業前の確認を怠らなければ…」「あの時、うっかり目を離さなければ…」と後悔しないように、電気工事を行う際には、下記のような対策を行うと良いでしょう。
- 作業前の確認・点検を徹底する
- 設備や機器の仕様や特徴を理解する
- 感電や転落など、十分な安全対策を講じる
- ヒヤリハットが発生した際には報告し、情報共有を行
十分な対策を行っていてもヒヤリハットは発生してしまいます。だからこそ、再発を防止するためには、それらを分析し、対策を関係者に周知していくことも重要です。しかし、報告書の作成から全体への共有には手間がかかるもの。
「報告書などの事務作業が大変…」
「関係者全員に情報共有するには伝え漏れもあるし、手間もかかる…」
…というケースには、効率的に関係者全員に周知できるように、施工管理ツールを活用するのがおすすめです。例えば、「DEN-UP」なら、日報などもスマホから入力できるので、作業中のヒヤリハットの報告や周知も効率的に共有することが可能。現場の安全対策にも有効です。
今回ご紹介したようなヒヤリハット事例から重大な事故へと発展させないようにするには、日頃からしっかりと作業者の安全意識を高めておくことが大切です。
電気工事のDXトータル支援サービス「DEN-UP(デンナップ)」

DEN-UPは、電気工事会社様に寄り添い、課題やお悩みをDXで解決するためのトータル支援サービスです。異なる機能を持つ以下のアプリケーションをまとめてご利用いただけます。
- 施工管理に役立つ「KANNA」
- 写真管理ができる「PhotoManager」
- 人材育成を支援する「電気工事のまなび場」
- ビジネスマッチングの「CraftBank」
DEN-UPなら、各ツールで登録した案件を紐づけて管理・閲覧できる「DEN-UP
ConnecT」という独自機能を使ってKANNAとPhotoManagerを連携させることにより、案件情報と現場の写真を一元管理することも可能です。
「DXに興味があるけど、何から始めればいいのかわからない」「直感的に使用できる、操作しやすいツールでDXを進めたい」とお考えの電気工事業者様は、電気工事にまつわる業務の効率化と生産性の向上、人手不足解消に役立つDXツール・DEN-UPの導入をぜひご検討ください!
経営課題への対策は、DEN-UPで
今のうちに取り組みましょう
