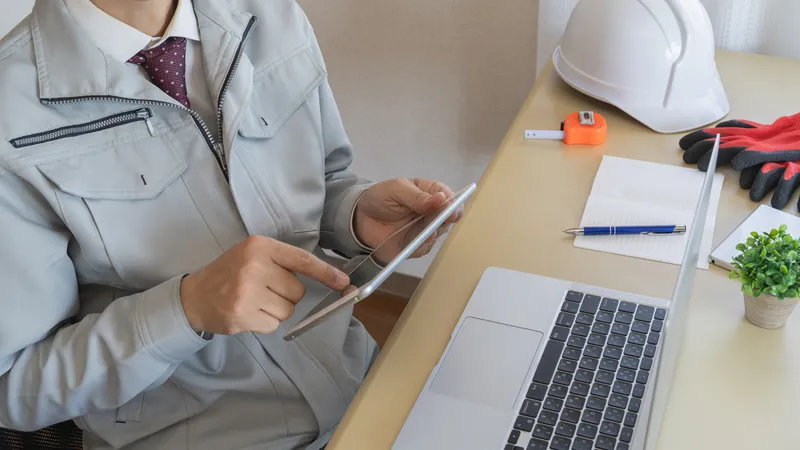
電気工事現場では、毎日のように大量の施工写真が撮影されます。そのため「どこに保存したか分からない」「社員によって管理方法が違う」など、整理に頭を悩ませる方は少なくありません。
しかし、写真は工事の記録や安全の確認、さらには発注者への報告や検査資料としても重要な役割を果たしますし、事故やトラブルを防ぐためにも、状況がわかりやすく整理されていることが求められます。
そこで本記事では、電気工事会社の経営者・現場責任者の方に向けて、撮影した工事写真を効率よく整理・管理するコツを解説します。さらに、写真整理や台帳作成が楽になる工事管理アプリもご紹介しています。
煩雑な写真管理を改善し、報告・証明・共有がスムーズに進む仕組みづくりのヒントとして、ぜひ参考にご覧ください。
- 1.電気工事における工事写真の役割と重要性
- 2.写真整理がうまくいかない理由
- 3.あとの整理を楽に!工事写真の撮り方のコツ
- 4.撮り方のコツ①撮影計画を策定する
- 5.撮り方のコツ②撮影イメージを決定する
- 6.撮り方のコツ③撮影機材を確認する
- 7.撮り方のコツ④画角・アングル・明るさに注意する
- 8.撮り方のコツ⑤5W1Hが読み取れる構図にする
- 9.撮り方のコツ⑥黒板や添尺を活用する
- 10.撮り方のコツ⑦ゴミや不要なものは写さない
- 11.工事写真を上手く整理するコツは?
- 12.写真整理のコツ①場所と時系列ごとにまとめる
- 13.写真整理のコツ②命名規則やフォルダ分けの基準を決める
- 14.写真整理のコツ③データのバックアップを実施する
- 15.写真整理のコツ④スマートフォンやタブレットで撮影する
- 16.写真整理のコツ⑤写真管理アプリや工事管理アプリを活用する
- 17.現場が変わる!工事写真の管理が可能なおすすめアプリ
- 18.施工案件の情報管理アプリ「KANNA」
- 19.現場写真管理ツール「PhotoManager」
- 20.電気工事のDXトータル支援サービス「DEN-UP(デンナップ)」
電気工事における工事写真の役割と重要性
工事写真は工事の進捗状況や品質を客観的に記録・証明するための重要な資料で、現場監督や施工担当者、場合によっては監理者が撮影を担当し、事前に作成した撮影計画書に基づいて、原則無加工で撮影・保存します。そして、撮影した工事写真は、工事写真台帳として整理・提出するのが一般的です。
工事写真の主な目的は、工事の「出来高管理」や「品質管理」を行うこと。さらに、工程全体の記録や、使用材料・施工部位の確認、トラブルや災害発生時の証拠保全、竣工後の維持保全、将来の補修や改修時など、幅広いシーンで活用されます。
特に、壁内や天井裏などの完成後に目視できない箇所の状態については、写真での記録が唯一の確認手段となります。
写真整理がうまくいかない理由
写真整理が後回しになりやすい理由として、以下のようなことがあげられるでしょう。
- 撮影のタイミングやルールが決まっていない
- 撮影したまま端末に放置されている
- フォルダやファイル名の項目がバラバラで探しにくい
- 撮影者ごとに管理方法が異なり、引き継ぎができない
- 編集や圧縮などの作業に時間がかかる
これらの要因が積み重なった結果として、いざ台帳や報告資料を作ろうとしたときに「必要な写真がない」「どの写真が何を写しているかわからない」といった問題が起きてしまいます。逆にいえば、これらの問題を解消することで、写真は格段に整理しやすくなります。
あとの整理を楽に!工事写真の撮り方のコツ

とはいえ、現場が忙しくなればなるほど、写真整理の優先順位は低くなってしまうもの。このような悩みを解決するには、あとから保管・整理方法が楽になるように、あらかじめ撮影段階から整理を見据えて撮影するのがポイントとなります。
そこで次に、公共工事にも対応できるように基本を押さえつつ、効率的に写真整理をするための撮影のコツについて見ていきましょう。
撮り方のコツ①撮影計画を策定する
工事写真は「いつ・どこで・何を撮るか」を明確にすることが最重要となります。仕様書や工程表をもとに撮影対象を洗い出し、チェックリストや計画表にまとめて、抜け漏れを防止しましょう。
また現場では、写真を撮ったその場でリストと照らし合わせて確認します。後から「あの工程の写真がない!」「写真の枚数が足りない!」といった事態を防ぐことができ、作業効率がアップします。
撮り方のコツ②撮影イメージを決定する
いきなり撮影するのではなく、同じ位置から撮影する「定点撮影」ができるように、撮影イメージを決めておくことが大切です。
完成形をイメージして、どの高さ・角度・画角で撮れば比較しやすいかを事前に検討し、施工前・中・後でアングルをそろえて撮影しましょう。
また撮影者が変わっても統一感が出せるように、イメージ写真やメモを共有しておくのもおすすめです。
撮り方のコツ③撮影機材を確認する
工事現場でありがちな機材トラブルや忘れ物を防ぐために、撮影機材の事前チェックは必須です。
スマートフォンやカメラなどの撮影機材が充電切れしていないか?SDカードは持参しているか?保存容量は十分に確保されているか?といったチェックに加えて、黒板・白板・三脚・スケールなどの補助道具も忘れずに準備しましょう。
特に公共工事では、撮影ルールに沿った機材が必要になるケースもあるため、契約書や工事計画書をよく確認しておくと安心です。
撮り方のコツ④画角・アングル・明るさに注意する
公共工事では、画像の明るさ補正やトリミングがNGとされることがあります。つまり、撮影時点で「使える写真」を撮ることが求められます。画角(全景・近影)やアングルなど、撮影前に必要な写真を改めて確認しておきましょう。
また、被写体が暗すぎたり、角度がずれていたりすると、使えない写真になってしまう恐れがあるので注意が必要です。なるべく自然光を取り入れる、照明器具を使う、手ブレを避けるなど、慎重な撮影を心がけます。
撮り方のコツ⑤5W1Hが読み取れる構図にする
写真1枚で「誰が(who)・いつ(when)・どこで(where)・何を(what)・なぜ(why)・どうやって(how)」が伝わる構図にすることも、整理しやすくなるコツの一つです。
撮影対象だけでなく、位置関係や背景情報、寸法を含めて撮ると、あとで写真を整理する際に役立ちます。
撮り方のコツ⑥黒板や添尺を活用する
工事写真では、黒板や添尺を使って撮影情報を補足します。
黒板に「工事名・工種・撮影日・施工箇所」などの情報を記入し、判読しやすい位置に配置してから撮影します。この時、黒板の文字が光で飛んでいたり、斜めすぎて読めなかったりするケースもあるので、角度や光量の調整にも気を配りましょう。
なお、電子小黒板付き写真撮影アプリを使えばあとの写真整理が格段に楽になります。
【PhotoManager(フォトマネージャ) for DEN-UP】
- 図面と紐づけた写真で工程管理ができる「現場写真管理ツール」
- 公共事業における最新の電子納品ガイドライン(国土交通省等)に対応
撮り方のコツ⑦ゴミや不要なものは写さない
現場写真にはゴミや私物、他業者の道具など、作業とは無関係な物が写り込むことがあります。
写真の信頼性を下げる原因にもなるため、不要物を取り除いてから撮影することを徹底しましょう。あとで写真を整理する際にも「これは必要な写真か?」と判断に迷わず、業務のスピードアップにつながります。
工事写真を上手く整理するコツは?

工事写真は単なる「記録」ではなく、トラブル発生時の証拠資料や社内ナレッジとしても活用されるなど、記録以上の価値がある重要な情報資産だといえます。
そのため「いざ探すと見つからない」「誰が撮ったか分からない」といった状態にならないように、大切なデータであるという意識を持って取り扱うことが大切です。
そこで次に、日々の業務の中で無理なく続けられる写真整理のコツについてご紹介します。
写真整理のコツ①場所と時系列ごとにまとめる
工事写真の整理は、撮影した写真を「場所」と「工事の進行順」に沿って分類することが基本です。
配線ルート別・階層別などの物理的な区分けに加え、「着工前→作業中→完了」のような時系列を意識すると、報告書作成や社内共有がスムーズになります。また、誰が見ても流れが分かる構成にすることで、確認作業の手間も減ります。
写真整理のコツ②命名規則やフォルダ分けの基準を決める
誰が整理しても同じになる状態を目指すには、たとえば【日付_現場名_工程名】というようにファイルや写真データの名前の付け方を決めておくことが大切です。また、フォルダの分け方を統一して、アクセスしやすい環境に整える必要もあります。
もし撮影者ごとに管理の方法がバラバラだと、一括管理が難しくなりますし、検索してもうまくヒットしないなど作業効率も悪くなります。
写真整理のコツ③データのバックアップを実施する
整理がうまくいっていても、データが消えてしまっては元も子もありません。USBメモリや社内サーバーのほか、クラウドストレージや外付けHDD(ハードディスク)などへの定期的なバックアップの実施を習慣づけましょう。
特に、スマホやタブレットで撮影した写真は端末に残りがちなので、自動同期設定やバックアップスケジュールを組んでおくと安心です。
写真整理のコツ④スマートフォンやタブレットで撮影する
工事現場での撮影は、デジカメではなくスマートフォンやタブレットを活用するのがおすすめです。スマホやタブレットだとその場でクラウドやアプリにアップロードでき、会社や事務所に戻ってからPCに取り込む手間が省けますし、端末内で現場名・日時などを記録しておけるため、写真台帳の下準備や証拠にもなります。
さらに、現場と事務所の情報共有がスムーズになり、工数削減にもつながります。
【関連記事】工事写真台帳の作り方とは?効率的に台帳作成するための6つの手順をご紹介
写真整理のコツ⑤写真管理アプリや工事管理アプリを活用する
整理の手間とミスを減らすには、写真管理アプリや工事管理アプリを導入するのも効果的です。
紙でのファイリングやExcel台帳では、保管スペースや人手がネックになりがちですが、写真管理アプリや工事管理アプリならクラウドに自動保存され、出先からでも閲覧・共有が可能になります。また5W1Hを写真と同時に入力できるアプリなら、記録漏れや整理ミスのリスク低減にもつながります。
導入コストは発生するものの、それ以上の大きな効果が期待できるでしょう。
現場が変わる!工事写真の管理が可能なおすすめアプリ

「写真整理がつい後回しになっている……」「人によって管理方法がバラバラ……」という状態が常態化していると、思わぬ事故やトラブルに見舞われたり、気づかないうちに時間のロスや伝達ミスが積み重なっている恐れが。
写真整理が可能なアプリを使えば「撮影→整理→報告」までを一本化することができ、業務効率が格段にアップしますし、写真が探しやすくなるのでいざという時にも困りません。
その他にも、
- 工事の全体像が把握しやすくなる
- 安全管理が徹底され事故リスクが低減できる
- 社内・社外の信頼度が向上する
- DX化に向けた第一歩が踏み出せる
といったメリットがあります。
私たちがご提供するDXトータル支援サービス「DEN-UP(デンナップ)」なら、写真管理アプリなどの工事に欠かせないツールを連携させて、案件情報を一元管理することができます。
施工案件の情報管理アプリ「KANNA」
KANNAは、案件別に顧客や物件情報を一括管理する、施工案件の情報管理アプリです。写真管理アプリと連携することで工事写真の整理に加えて、工事に関するさまざまな資料の整理や情報共有が、このアプリ1つで行えます。
【KANNAの主なサービス】
- 図面や写真等、案件に関わる各種資料の管理
- 工事のスケジュール共有や進捗状況の登録
- 日々の工事内容や工事に関する報告事項の記録
- 上記のような情報のリアルタイムでの共有
- チャット機能を使った関係各所とのやり取り
一般的なチャットツール等と操作性も近いため、特に「何からDXに着手すべきかわからない」「直感的に使用できるDXツールを探している」という電気工事会社様におすすめです。
現場写真管理ツール「PhotoManager」
PhotoManager(フォトマネージャ)は、写真を図面に紐づけて管理できる現場写真の管理ツールです。
スマホで電子小黒板アプリを起動して写真撮影すれば図面と紐づけて保存することができるので、各工程の写真の撮り忘れや管理の手間が削減され、事務作業や情報共有の効率化につながります。
さらに、パソコン専用ソフトとの連携で、公共事業における最新の電子納品ガイドライン(国土交通省等)に対応した台帳を簡単に作成することができます。
電気工事のDXトータル支援サービス「DEN-UP(デンナップ)」

DEN-UPは、電気工事会社様に寄り添い、課題やお悩みをDXで解決するためのトータル支援サービスです。異なる機能を持つ以下のアプリケーションをまとめてご利用いただけます。
- 施工管理に役立つ「KANNA」
- 写真管理ができる「PhotoManager」
- 人材育成を支援する「電気工事のまなび場」
- ビジネスマッチングの「CraftBank」
DEN-UPなら、各ツールで登録した案件を紐づけて管理・閲覧できる「DEN-UP
ConnecT」という独自機能を使ってKANNAとPhotoManagerを連携させることにより、案件情報と現場の写真を一元管理することも可能です。
「DXに興味があるけど、何から始めればいいのかわからない」「直感的に使用できる、操作しやすいツールでDXを進めたい」とお考えの電気工事業者様は、電気工事にまつわる業務の効率化と生産性の向上、人手不足解消に役立つDXツール・DEN-UPの導入をぜひご検討ください!
